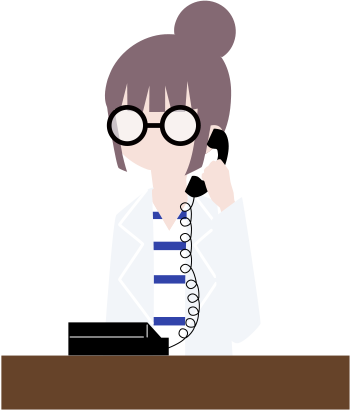今年もいろんなところで桜の開花宣言をし始めましたね。
でも、どうして桜は毎年、同じような時期に咲くのでしょうか?桜の開花には、気温や冬の寒さが深く関係しています。
今回は、桜がどのようにして咲く時期を決めているのかをご紹介します。
- 目次
-
- 1.桜はどうやって咲く時期を決めているの?
- 1.桜のつぼみは冬の間どうなっているの?
- 2.桜が咲くために大事な「休眠打破(きゅうみんだは)」とは?
- 3.なぜ暖かくなると咲くの?/li>
- 4.開花予想はどうやって決めるの?/li>
- 2.まとめ
桜はどうやって咲く時期を決めているの?
桜の木は、自分で「そろそろ咲く準備をしよう」と考えているわけではありません。実は、気温の変化を感じ取ることで、咲くタイミングを決めています。桜のつぼみは、冬の間じっと眠っていて、春になると少しずつ目を覚まして花を咲かせています。
桜のつぼみは冬の間どうなっているの?
桜のつぼみは、夏の終わりごろにすでに作られています。でも、すぐに花が咲くわけではありません。冬の寒さを経験することで、つぼみはゆっくりと成長を止め、春に向けてエネルギーをためます。この状態を「休眠(きゅうみん)」といいます。
桜が咲くために大事な「休眠打破(きゅうみんだは)」とは?
桜が花を咲かせるには、「休眠打破(きゅうみんだは)」という大事なステップが必要なんです。冬の間にしっかり寒さを感じることで、つぼみは「そろそろ春に向けて準備をしよう」と目を覚まし始めます。
この「目覚める」ことが、休眠打破です。
もし冬があまり寒くなかった場合、休眠打破がうまくいかず、桜の開花が遅れたり、花の数が少なくなったりすることもあります。
なぜ暖かくなると咲くの?
冬の寒さで目を覚ました桜のつぼみは、次に春の暖かさを感じることで成長を始めます。気温が一定以上になると、つぼみの中で花が咲く準備が進み、やがて開花します。そのため、春の気温が高いと桜が早く咲き、逆に寒い日が続くと開花が遅くなることもあります。
開花予想はどうやって決めるの?
毎年、ニュースなどで「桜の開花予想」が発表されますが、これはどのように決められているのでしょうか?
開花予想では、冬の気温がどれくらい低かったか(休眠打破の進み具合)や春になってからの気温の上がり方を計算します。特に「積算温度(せきさんおんど)」という考え方が使われ、一定の温度を超えると桜が咲くと予想されるのです。
積算温度は、ある一定の基準を超えた気温を毎日合計していったものです。たとえば、桜の開花予想では「1日の平均気温が0℃以上の日の温度」を積み重ねて計算します。桜の場合、積算温度が約600℃~800℃に達すると開花するといわれています。このため、気温の上がり方が早い年は桜の開花も早くなり、寒い年は開花が遅くなります。
まとめ
桜が咲くには寒い時期が必要なんですね。
積算温度で桜が咲く予想ができるので来年はやってみようと思います。いまから、来年の桜の時期が待ち遠しいです!!
弊社では、IoT機器を販売・開発しております。ご相談やご質問をお待ちしております。お気軽にお問い合わせください。