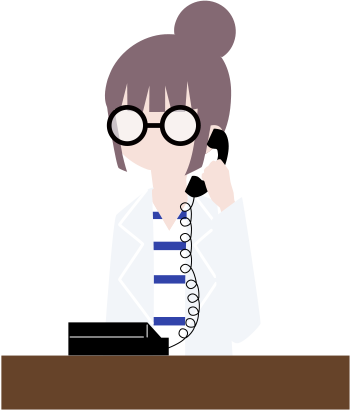外を見てみると、今日は空にたくさん雲があるけれど、晴れって言ってたなぁ…なんて思ったことはありませんか?空がグレーに見える日は、「今日は曇りだな」と感じたこともあるかもしれません。
でも、「曇り」と「晴れ」のちがいって、どこで決まるのでしょう?どちらにも「雲」があるのに、どうやって見分けるのでしょうか。
今回は、そんなふしぎな「雲と天気の関係」について、お話ししていきます。
- 目次
-
- 1.曇りの日と晴れの日、どちらにも「雲」があるの?
- 1.曇りの時の雲はどんな雲?
- 2.晴れの時の雲はどんな雲?
- 2.雲の高さや量がカギだった!
- 1.そもそも雲ってどうやってできるの?
- 3.曇りと晴れを見わける天気予報のルール
- 4.まとめ
曇りの日と晴れの日、どちらにも「雲」があるの?
「晴れの日」でも空には雲があることが多いです。まっ青な空にぽつんと雲が浮かんでいるのを見たことがある人もいるでしょう。でもその一方で、「曇りの日」も空に雲があります。
どちらも雲があるのに、どうして「晴れ」と「曇り」に分けられるのでしょう?そのカギは、「雲の量」と「空の見えかた」にあるんです。
曇りの時の雲はどんな雲?
曇りの日は、空の大部分が雲でおおわれています。
たとえば、空を見上げても青い空がほとんど見えなくて、空全体がグレーや白っぽくなっているとき、それが「曇り」です。太陽の光も、雲にさえぎられて弱くなり、空がなんだかどんより見えます。このときに出ている雲は、空に広がるようなうすい雲やどっしりとした厚い雲が多いです。
晴れの時の雲はどんな雲?
一方で、晴れの日にも雲があることがありますが、その雲は空のほんの少しにしかありません。ぽかぽかとした天気の中で、空にポツポツと白い雲が浮かんでいることってありますよね?それが「晴れの時の雲」です。空の多くの部分が青く見えて、太陽の光もしっかりと感じられるときは「晴れ」と呼ばれます。
雲の高さや量がカギだった!
気象の世界では、「空のうち、どれだけの部分が雲におおわれているか」で天気が決まります。たとえば、空の8割以上が雲で見えないと「曇り」、2割しか雲がないなら「晴れ」と判断されます。
つまり、空の見た目の「雲の量」が天気を分けるポイントなんです。
また、雲の「高さ」も関係します。高いところにある雲は太陽の光を通しやすく、空が明るく見えます。でも、低いところにどっしりとある雲は光を通しにくく、空が暗く見えます。これも、晴れと曇りを見分けるポイントのひとつです。
そもそも雲ってどうやってできるの?
雲は、空気の中の水分が集まって小さな水のつぶや氷のつぶになったものです。おふろのあとに鏡がくもるのと、よくにています。あたたかい空気が上にのぼって冷やされると、水分が水のつぶになって空に浮かびます。これが雲です。
曇りと晴れを見わける天気予報のルール
天気予報では、空を「10分割」して、そのうち何割が雲でおおわれているかを見て判断しています。たとえば、空のうち9割が雲におおわれていたら「曇り」、1割しか雲がなければ「晴れ」と言うのです。このルールを使って、予報士さんたちは天気を見わけています。
まとめ
たくさんの雲で空が白っぽく見えるときは「曇り」。少しだけ雲があって、青空がたくさん見えるときは「晴れ」。空の何割が雲で覆われているかで曇りか晴れが決められていたんですね。
空を見上げて、「今日はどんな雲が出ているかな?」と気にしてみると、天気のことがもっと楽しく感じられるかもしれませんね。弊社では、IoT機器を販売・開発しております。ご相談やご質問をお待ちしております。お気軽にお問い合わせください。