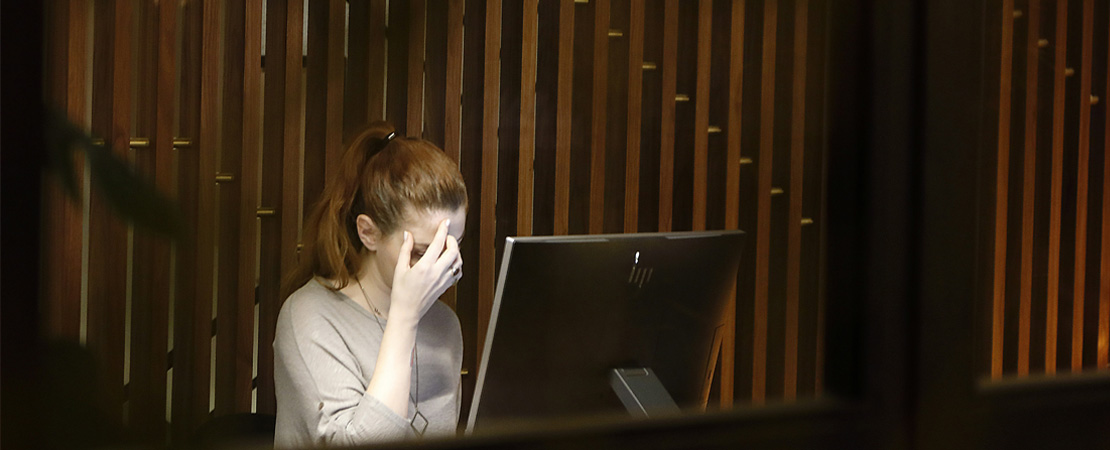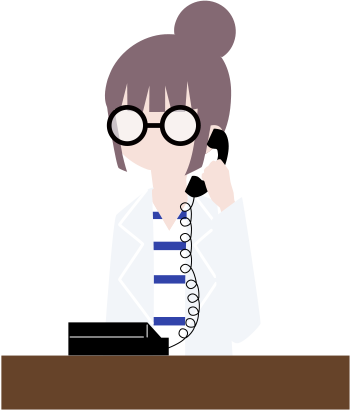秋の風が少し冷たくなるころ、柿の木にはオレンジ色の実がぽつぽつと光ります。見上げてみると、木の上のほうにばかり実がついていて、下の枝にはあまり見当たりません。
「なんで上だけ?」と不思議に思ったことはありませんか?
実はこれ、ちゃんとした理由があるんです。
- 目次
-
- 1.柿が上の方にできる「3つの理由」
- 2.もう少し詳しいしくみ
- 1.葉と光合成の役割
- 2.木の中の栄養の流れ
- 3.枝の強さと実のつき方
- 3.なぜ下の枝にはあまり実がならないの?
- 4.まとめ
柿が上の方にできる「3つの理由」
まず一番の理由は、太陽の光です。
植物は光を浴びて「光合成」という働きをし、空気と水から栄養を作り出します。葉っぱが太陽の光をたっぷり受けるほど、元気なエネルギーを作ることができます。
木の上の方は、ほかの枝や葉に邪魔をされず、光をたくさん浴びられる場所です。だから上の枝のほうが、実を育てる力が強くなるります。
次に大事なのが、木の中を流れる栄養と水の通り道です。
根っこが吸い上げた水やミネラルは、「道管」を通って枝や葉に運ばれます。そして、葉っぱで作られた栄養は「師管」という道を通って、実や根っこに届けられます。
上の枝は若くて勢いがあり、この流れがスムーズです。だからこそ、実を育てるための栄養が届きやすいんですね。
とはいえ、木の栄養は全体でバランスをとって流れています。特に、近くの葉で作られた栄養は、その近くの実に届きやすいという性質があるとも言われています。
そして三つ目の理由は、枝の成長のしかたです。
木の枝には「頂芽優勢」という性質があって、上にある芽ほどよく伸びます。上の枝がぐんぐん育つのは、この性質のおかげです。
さらに、上の枝は新しくて丈夫で太く育っているので、重たい実をしっかり支えることができます。
つまり、上の枝は「光を浴びやすく」「栄養が届きやすく」「枝が強い」。この三拍子がそろっている場所なんです。
もう少し詳しいしくみ
葉と光合成の役割
葉っぱは、木の“工場”のような存在です。
太陽の光をエネルギーに変えて、木全体を元気にしてくれます。上の枝の葉は日当たりがよいので、光合成が盛んに行われます。そこで作られた栄養が、すぐ近くの実に流れ込み、甘くて立派な柿を育ててくれるのです。
木の中の栄養の流れ
木の中では、道管と師管という“二本のすじ”がはたらいています。
道管は水を、師管は葉っぱで作られた栄養を運ぶ通り道です。上の枝ではこの流れがスムーズで、実が育つのに必要なものがたっぷり届きます。
特に、光の当たる枝と実の距離が近いほど、育ちが良いといわれています。
枝の強さと実のつき方
実がなるには、枝の強さも大切です。
上の枝は若く、木の勢いがあるため太くて丈夫です。だから実をたくさん支えられます。
逆に、下の枝は年を重ねて弱っていたり、光が届きにくかったりするので、どうしても実が少なくなりがちです。
なぜ下の枝にはあまり実がならないの?
下の枝は、上の葉や枝に光をさえぎられて、光合成がうまくできません。
また、古くなった枝は栄養や水の流れも悪くなり、実を育てる力が弱まります。
ただし、農家さんたちは剪定という作業で枝を整え、下の枝にも光が届くように工夫しています。上手に手入れすれば、下の枝にもちゃんと実がなるんですよ。
まとめ
柿の実が木の上の方にできるのは、太陽の光がよく当たり、栄養が届きやすく、枝が強く育つためでしたね。
次に柿の木を見かけたら、ぜひ上を見上げてみてください。
太陽の光をいっぱいに浴びて、誇らしげに実った柿がいっぱいなっていると思います。
弊社では、IoT機器を販売・開発しております。ご相談やご質問をお待ちしております。お気軽にお問い合わせください。