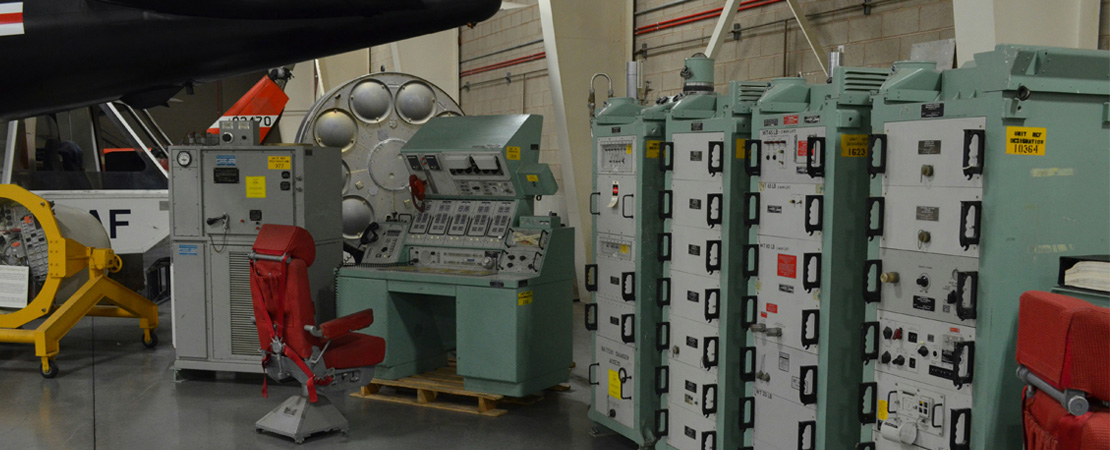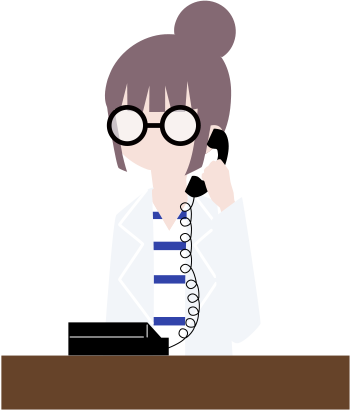今の世の中、いろんな場面で「データ」が使われています。
たとえば、学校のテストの点数やお店で売れた商品の数、家で使った電気の量なども全部データです。でも、データを集めるだけで満足してしまっていることって、結構あるんです。せっかく集めたのに、そのあと何もしていなかったら、ちょっともったいないですよね。
この記事では、「データを集めたあと、どうすればちゃんと活かせるのか?」について、ご紹介します。
- 目次
-
- 1.なぜ「集めただけ」で終わってしまうの?
- 2.活かすための5つのステップ
- 3.気をつけたい“落とし穴”
- 4.道具よりも“考え方”が大事
- 5.まとめ
なぜ「集めただけ」で終わってしまうの?
たとえば、夏休みの自由研究で毎日の気温を記録したとします。でも、ただ数字を並べただけでは、何がわかったのか伝わりませんよね。
「今年の夏は、いつが一番暑かったのか?」とか「雨の日は気温が下がるのか?」といったことを調べてみてこそ、意味のある研究になります。
同じように、会社や学校でも、せっかくデータを集めても「ふーん、そうなんだ」で終わってしまうことがあります。どう使ったらいいのか分からなかったり、「とりあえず集めただけ」で満足してしまったりするのが、その理由です。
活かすための5つのステップ
1.「何のために使うのか」をはっきりさせること
ただ集めるだけじゃなくて、「もっと売れるお店にしたい」とか「授業でつまずく子を減らしたい」といった目的があると、データの見方も変わってきます。
2.「本当に大事な情報を見つける」こと
たくさんの数字の中でも、自分の目的に関係あるものだけを見るようにすると、迷わずにすみます。
3.「見やすくまとめる」こと
グラフや表にしたり、言葉で説明したりすると、ほかの人とも共有しやすくなります。
4.「そこから行動を考える」こと
たとえば「朝の時間にお店がすいてる」とわかったら、朝にセールをやってみる、みたいな工夫ができます。
5.「やってみた結果をまた見直す」こと
行動して終わりじゃなくて、「うまくいったかな?」と確認することで、次につなげることができます。
気をつけたい“落とし穴”
データを活かすとき、いくつかの落とし穴にも注意が必要です。
たとえば、データが間違っていたり、一部しか見ていなかったりすると、まちがった判断をしてしまうことがあります。また、「数字だけで全部わかったつもりになる」のも危ないです。
たとえば、お店の満足度が90点だったとしても、実際に来た人の感想を読んでみると、「スタッフの対応がちょっと冷たかった」という声があるかもしれません。そういう声こそ、データでは見えにくいけれど大事なヒントになります。
道具よりも“考え方”が大事
最近では、データを集めたり分析したりできる便利なツールがたくさんあります。でも、どれだけ良い道具があっても、「このデータをどう活かすか」を考える気持ちがなければ、意味がありません。
たとえば、クラス全員がテストの点をグラフで見られるようになったとしても、「ふーん」で終わってしまったら、変化は起きません。でも、「この結果をどうよくしていこうか?」とみんなで話せる空気があると、小さな気づきから大きな変化が生まれます。
これは会社でも同じで、「数字を見て終わり」ではなく、「チームで考える文化」があると、自然と行動が変わっていきます。
まとめ
データは、ただ集めただけではもったいないものです。本当に大切なのは、それをもとにどう動くかです。
目的を決めて、大事なところを見つけて、見やすくまとめて、行動して、見直す。そうやってデータを“活かす”ことで、毎日の仕事や生活がもっと良くなっていきます。
そして何よりも、「どう使えばいいかな?」と考え続ける気持ちが大切です。数字の中には、気づかなかったヒントがたくさんかくれています。あなたのまわりのデータも、もしかしたら新しいアイデアにつながるかもしれませんよ。
弊社では、IoT機器を販売・開発しております。ご相談やご質問をお待ちしております。お気軽にお問い合わせください。