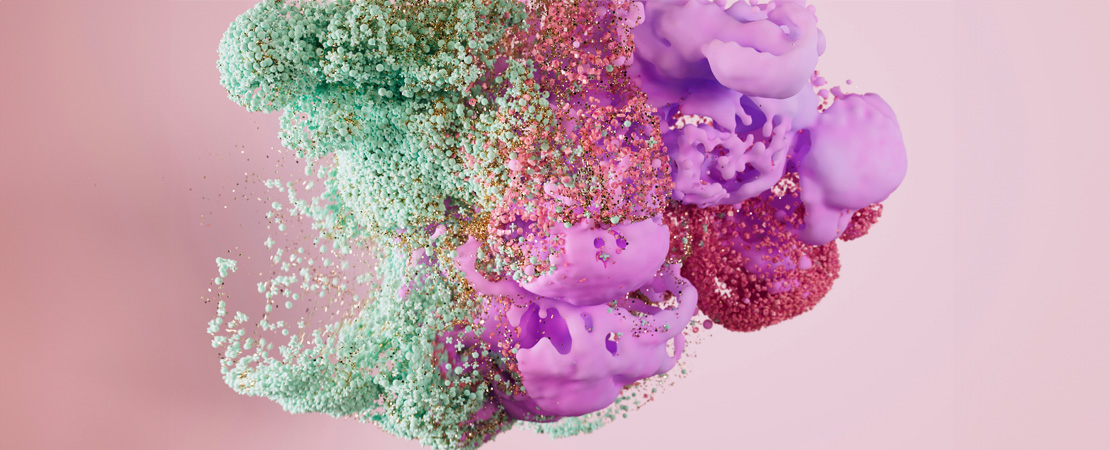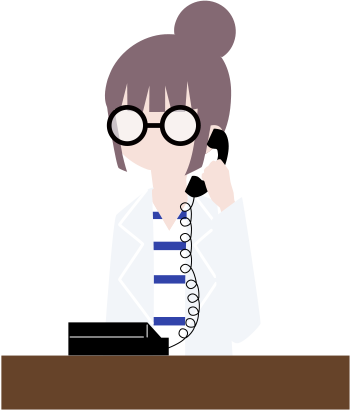IoTやセンサー技術の進化により、工場やビルでは設備の状態が「見える化」されるようになってきました。温湿度やCO2濃度、エネルギー使用量…。これまで感覚や経験に頼っていた部分が、数値で見えるようになりました。
ですが、
「グラフは出ているけど、だから何?」
「データを見ても、現場では何も変わっていない」
そんな声が、聞こえてくることもあります。
“見える化”はできたのに、“改善”にはつながらない。いったい何が起きているのでしょうか?
- 目次
-
- 1.なぜ「見える化」は改善につながらないのか?
- 壁①:目的が曖昧なまま見える化してしまっている
- 壁②:データの意味が現場に伝わっていない
- 壁③:見るだけで終わり、改善アクションにつながらない
- 2.データを“改善”につなげる3つのヒント
- 1.「なぜ見える化するのか」を明確にする
- 2. 現場と一緒に“意味づけ”をする
- 3. アクションと連動したルールを決める
- 3.「見える化」はスタート地点。
なぜ「見える化」は改善につながらないのか?
データを集めるところまではうまくいっても、その後の運用や改善に結びつかない理由には、いくつかの共通した“壁”があります。
壁①:目的が曖昧なまま見える化してしまっている
「とりあえずセンサーを入れて、ダッシュボードを作った」
そのように、明確な目的を持たずに見える化を始めてしまうと、後から「この数字、何に使えばいいの?」ということになりがちです。
「エネルギーを見える化したい」だけでは不十分です。
省エネなのか、快適性なのか、故障予知なのか。
目的が定まっていなければ、見るべき指標や判断基準もぼやけてしまいます。
壁②:データの意味が現場に伝わっていない
「管理部門ではグラフやアラートを見て状況を把握できていても、実際に設備を操作したり点検したりする現場の作業員が、その意味を理解できていないことは多くあります。
たとえば・・・
管理者:「この日、空調の消費電力が急に上がっています」
現場担当:「でも、特に異常はなかったと思いますけど…」
このようなすれ違いは、データの背景にある“行動”や“判断基準”が共有されていないことに起因しています。
「グラフが赤くなったら、具体的に何をするのか?」が明確になっていないと、現場は動けません。
壁③:見るだけで終わり、改善アクションにつながらない
導入当初は注目されていたダッシュボードも、「見るだけ」で終わってしまえば、次第に開かれなくなります。
よくあるのは、こういった状態
- グラフは定期的に更新されている
- でも、その数字を見て“誰が何をするか”が決まっていない
- 異常値が出ても、「誰も責任を持って動かない」
こうなると、せっかくのデータも、何の役にも立たなくなってしまいます。
データを“改善”につなげる3つのヒント
1.「なぜ見える化するのか」を明確にする
改善につなげるためには、まず目的を明確にすることが最重要です。
- 「電気代を前年比5%削減する」
- 「快適性スコアを月間で90点以上に維持する」
- 「空調の無駄稼働を週3件以下にする」
このように、“何をどう改善したいのか”を具体的に決めておくことで、見るべきデータも、自ずと明確になってきます。
2. 現場と一緒に“意味づけ”をする
集めたデータは、“数字”のままでは意味がありません。
その数字がどんな現場の動きと関係しているのかを、人が読み解いてこそ価値が生まれます。
おすすめなのが、「月に1回の振り返りミーティング」。
- 消費電力が急に上がった日があれば、なぜかをみんなで考える
- 湿度が下がった理由を設備の運転や作業内容と照らし合わせて振り返る
こうした対話を通じて、“現場の感覚”と“データ”をつなげる土壌が育っていきます。
3. アクションと連動したルールを決める
データを活かすには、「数字に応じた具体的な行動」が必要です。
- 電力量が一定値を超えたら、◯◯を停止する
- 湿度が40%を切ったら、加湿器を作動させる
- エラーが出たら、LINEで通知&当番がチェックする
こうした“判断の自動化”や“アクションのルール化”があると、データが“見える”だけでなく、“動ける”ようになります。
「見える化」はスタート地点。
IoTやデジタル技術は、データを集めることは得意ですが、それをどう読み解き、どう動くかは、人の力が必要です。
“見える化”はゴールではありません。
データの意味を共有し、仕組みとして動かすことが改善への第一歩です。
あなたの現場でも、見える化で止まっていませんか?
次に進むヒントは、意外と身近なところにあるかもしれません。
弊社では、IoT機器を販売・開発しております。ご相談やご質問をお待ちしております。お気軽にお問い合わせください。